- Home>
- 人を育てる/人材育成>
- 現場でコーチングとティーチングをどのように使う事が有効か?
現場でコーチングとティーチングをどのように使う事が有効か?
2018.11.12

コーチングとティーチングは、ともに対象者の目標を達成へと導くために行われますが、
アプローチの仕方はそれぞれ違います。
現場でコーチングとティーチングをどのように使うことが有効なのか、検証して行きたいと思います。
1.コーチングとティーチングの比較
コーチングは、「相手(個人・組織)の主体性を引き出し、目標達成に導くこと」
ティーチングは「自分が持っている知識、技術、経験などを相手に伝えること」
と定義しています。
※「コーチングとは」参照
コーチングとティーチングの成果や関わり方の違いは、下図のとおり比較できます。
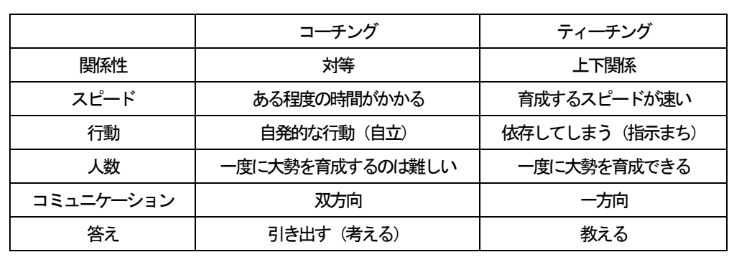
コーチングとティーチングとでは、成果や関わり方に違いがあるのがおわかりいただけたでしょうか?
では、コーチングとティーチングはどの様な時に行うのが効果的に機能するのか?
「2.仕事のリスクと能力・スキルの四象限マトリクス」にて説明して行きます。
2.仕事のリスクと能力・スキルの四象限マトリクス
コーチングとティーチング、どちらのアプローチを使うのかは、仕事のリスクやその人が持っている
能力(スキル)によって異なります。
その目安となるのが、次のマトリクスです。
どの様な特徴があるのか、具体的に説明して行きましょう。
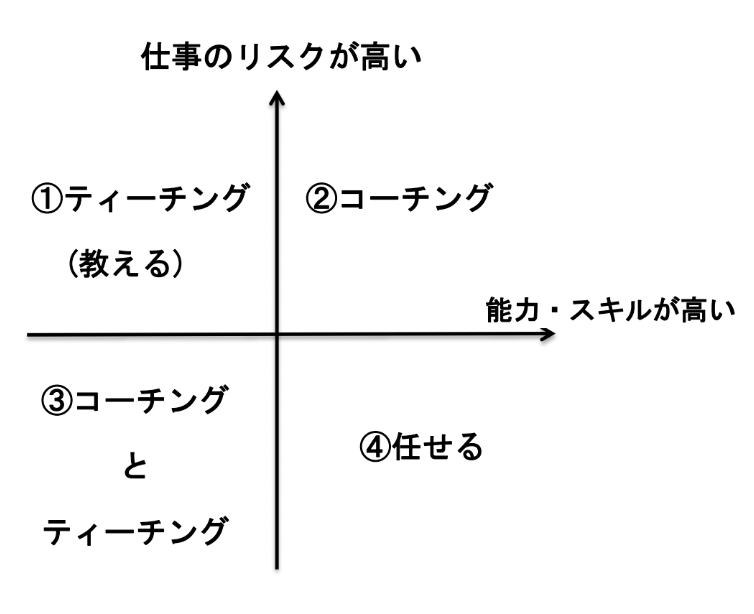
①ティーチング(教える)
仕事のリスクが高く、能力・スキルが低い場合は「ティーチング」が最も適します。
お客様のクレームや事故など、すぐに対応しないといけない時は、経験豊富な熟練者から具体的に
行動を教えてもらう方(指示)が、効率的で二次災害などを防ぐことができます。
また、経験の浅い社員に対してある一定レベルに能力・スキルを引き上げるには、
ティーチングの方が機能します。
②コーチング
仕事のリスクが高く、能力・スキルが高い場合は、基本的には「コーチング」が最も適する領域です。
クレームや事故などの経験を通して、
「この経験で何を学んだのか?」「この経験で、どうしてそう感じたのか?」
「よりよくするために、私たちはどの様に取り組むのか?」
と問いかけることで、改善点が明確になります。
そして、未来のイメージを具体化する関わりによって将来の夢やビジョンなど、
すぐには必要ではないが、企業にとって重要と感じる事柄にもコーチングは有効です。
③コーチングとティーチング
仕事のリスクが低く、能力・スキルが低い場合は、「コーチングとティーチング」を使い分ける方が、
効果的です。新入社員に対する教育などがあてはまります。
一定レベルに能力・スキルを引き上げるために、ティーチングを行います。そして、本人の自発的な行動を促し、自ら考え行動できる人材に育成するために、コーチングも並行して行います。
④任せる
能力・スキルが高い人が、仕事のリスクが低い事を行う場合は、一般的に任せる方がよいでしょう。
3.現場で活かす、コーチングとティーチングの具体例
実際に、コーチングとティーチングをどの様に現場で活かしていけばいいのでしょうか?
仕事のリスクと能力・スキルの四象限マトリクス
①ティーチング(教える)、②コーチング
について事例をもとに、説明します。
【ケース 1】①ティーチング(教える)
食品会社の通販部門にて、明日の原稿締め切りの企画があります。
締め切り日が過ぎてしまうと、印刷が遅れ、カタログの配送、商品の受注発注、倉庫での作業など、
すべてにおいて遅れてしまいます。結果、お客様に多大な迷惑をかけてしまいます。
そんな中、新しく担当になったIさんは何を基準に商品を選定してよいか解らず、時間ばかりが過ぎ、
焦ってあなたの元に相談に来ました。
このケースは、先ほどのマトリクスでいくと、①ティーチング (教える)になります。新しく担当になった為、Iさんは現状何を基準に商品を選定していいかわからない状態です。納期が迫ってきている以上、
ここは上司が商品を選定する基準を教え、基本的には手取り足取り教えるのが効率的です。
【ケース 2】②コーチング
先ほどのIさんが、選定基準をについて上司であるあなたに相談に来ました。
今回の経験を活かして、次回は同じミスを犯したくないと伝えてきました。
Iさんは社歴も長く、社員たちから人望もある有能な社員です。
このケースは、先ほどのマトリクスでいくと、②コーチングの領域になります。
場合にもよりますが、基本的には「コーチング」が最も適する領域です。
「この経験で何を学んだのか?」
「経験して、どうしてそう感じたのか?」
「よりよくするために、私たちはどの様に取り組むのか?」
Iさんの全脳にアプローチし、改善点を明確化することが効果的です。
もちろん、Iさんがアドアイスを求めてきたら、アドバイスを行う事もOKです。
基本的にはコーチングのスタンスで向き合うのが効果的なケースと言えます。
まとめ
相手の(個人・組織)の主体性を引き出し、目標達成に導くことができるリーダーは、
従来の育成法である「ティーチング」ともう一つの育成手法である「コーチング」を状況や
相手に似合わせ効果的に使い分けます。
そして、コーチングとティーチングの両方のメリットを臨機応変に活用することで、
相手(個人・組織)のパフォーマンスを向上させ、目標達成へと導いていきます。
これは企業など組織の一例です。
学校では[先生と生徒]、家庭では[親と子ども]に置き換えて
関係性を考えてください。
![]()
![]() Mail Magazine無料メルマガ
Mail Magazine無料メルマガ
Sachi流 元気が出るプチコーチング
最新情報を配信! ぜひご登録ください。
人気の記事 TOP5
- 相手を認めるってどういうこと?2018.11.26
- 「学習の5段階」を理解し成長を促す2025.06.01
- 決まってない自分を受け入れる勇気 —— 中腰力のすすめ2025.09.01
- 相手の心を満たす肯定的ストロークとは?2018.11.27
- 異文化コミュニケーション「アピールは苦手!? 木を見て森を見ずが伝わる?」2019.11.01
オススメ記事
- 自律的な人材・組織を創る2022.05.01
- SEIFISH(セルフィッシュ)になる2020.08.01
- 「ニューノーマル」の時代2020.05.01
- 心技体2020.04.01
- AIとコミュニケーション2019.12.01








